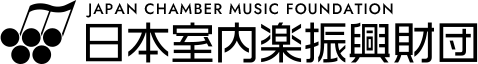アタッカ・クァルテット インタビュー
過去と現代の作曲家の対話を求めて グラミー賞に輝く 弦楽四重奏団
インタビュアー:後藤菜穂子
コロナ禍での公演延期を経てようやく実現した、「トップ・アンサンブル・シリーズ」のアタッカ・クァルテット公演(2022年9月12日、あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール)。ツアー途中にヴィオラ奏者のネイサン・シュラムが家族のご不幸のために帰国を余儀なくされたが、牧野葵(き)美(み)という頼もしい代役を得て、独自のサウンドワールドで聴衆を興奮させた。公演前に3人のメンバーに話をうかがった。



——第7回大阪国際室内楽コンクールについてはどんな思い出がありますか?
アンドリュー・イー[以下、アンドリュー]:2011年、震災からまだ間もない頃だったことをよく覚えています。参加を取りやめた団体もあり、どこに行っても「来てくれてありがとう」と言われたことが印象に残っています。会場にもとても重苦しい雰囲気が漂っていました。私たちは本選でベートーヴェンの後期の弦楽四重奏曲を演奏したのですが、聴衆の皆さんの思いが私たちの演奏にも浸透してくれたように思えました。音楽作品というのは、音楽家と聴衆のあいだに存在するのだということを強く感じた体験でした。
エイミー・シュローダー[以下、エイミー]:そのとき弾いたのはベートーヴェンの弦楽四重奏曲作品132でした。私たちはコンクールの前にこの曲を仕上げようと、事前に何回か演奏会でも弾いたのですが、みんなまだ若く、こうしたタイプの曲に取り組むのが初めてだったので、満足のいく演奏ができていませんでした。日本に着いてからも時差ボケやら予選やらで、仮に本選に進めたとしても本当に弾けるんだろうかと不安でした。ところが本番の舞台の上で、私たち4人と聴衆のあいだで何かが起こり、すべてがうまくいったのでした。こうした奇跡はコンサートでは起きても、コンクールの舞台で可能だとは思ってもみませんでした。そしてこの体験を通じて、私たちは初めてベートーヴェンを真に身近に感じられるようになったのです。
アンドリュー:私たちはたくさんの弦楽四重奏曲のコンクールを受けましたが、正直、どれもとても辛い体験でした。でも、コンクールのために曲を入念に準備して完璧に仕上げたことで、私たちは世界の舞台への通行証を手にできたともいえるのです。特に大阪は、グループにとって決定的な何かが起きた特別な大会でした。その意味ではコンクールに出場したことはかけがえのない体験になりました。
—大阪での優勝によって、どんな道が開かれましたか?
エイミー:第一に、たくさんのクァルテットの仲間と知り合うことができましたし、また尊敬する審査員の方々とお話をする機会もいただけました。そして何よりも日本とのつながりができて、これまでに何度もこのすばらしい国を訪れることができ、本当に嬉しく思っています。このコンクールは米国でもたいへん高く評価されていますので、優勝をきっかけに母国でもさまざまな演奏の機会を得ることができ、活動の場が広がりました。
——ドメニクさんは2020年2月にアタッカ・クァルテットに第2ヴァイオリン奏者として加わりました。グループとの出会いは?
ドメニク・サレー二[以下、ドメニク]:私がアタッカ・クァルテットに初めて出会ったのは2007年、コネティカットのノーフォーク室内楽祭でのことでした。当時、私自身も別の弦楽四重奏団のメンバーとして参加していたのですが、アタッカの演奏を聴いて本当に驚嘆しました。その時に彼らが演奏していたのはバルトークの弦楽四重奏曲第4番だったのですが、それまで彼らのようなサウンドを聴いたことがなかったのです。型にはまらず、その場への深い理解と、インスピレーションと自発性に満ちた演奏でした。私たちはその時にクァルテットで弾くことの意義をあらためて認識したのです。それから10年以上がたち、このグループに加わることができて本当に光栄に思います。

——アタッカ・クァルテットは、いわゆるヨーロッパ・スタイルの伝統的な弦楽四重奏団とは一線を画した活動を展開してきました。結成当初からそうした構想を持っていたのでしょうか?
アンドリュー:私たちがグループを結成した2003年と2022年では弦楽四重奏を取り巻く環境は驚くほど変わりました。20年前、有名な弦楽四重奏団といえばジュリアードやエマーソンら、両手で数えられるぐらいで、プロのクァルテットとして活動するということは現実的ではなかったのです。私たちも最初は彼らと同じく、ハイドン、バルトーク、ベートーヴェンなどを弾いていました——それはどの若いクァルテットも通る道でしたから。
もちろん、当時もアルディッティQやクロノスQなど現代ものに特化したグループもいましたが、私たちはその両方のレパートリーがやりたいと思っていました。やがて、メトロポリタン美術館などのレジデント・クァルテットとして自分たちのコンサート・シーズンを持てるようになったことで、プログラミングに冒険できるようになり、ジョン・アダムズやキャロライン・ショウら、現代のものを導入していったのです。
ドメニク:今では、特にヨーロッパに招かれる時には、アメリカの音楽を演奏してほしいとリクエストされることが多いです、たとえば昨秋、ドイツのテューリンゲン・バッハ週間に招かれ、ヴァイマールの歴史的な建物でオール・キャロライン・ショウのプログラムを演奏しました。どのように受け止められるか不安でしたが、拍手が鳴り止まず、3曲もアンコールをしました。
その一方で、今回の日本での公演のように、ベートーヴェンとポール・ウィアンコやショウの作品を並べて演奏すると、過去と現代の作曲家たちとのあいだに対話が生じておもしろいと思います。私たちにとってもベートーヴェンの「ハープ」の次に音による壮大なドラマともいえるウィアンコの「弁慶の立ち往生」を——作品の舞台である日本で——体験できたのは本当にすばらしいことでした。
私自身は今回初めて日本を訪れましたが、日本の聴衆はどこよりもあたたかく教養があり、期待に満ちた表情で聴いてくださいました。他の国とくらべるわけではありませんが、日本の聴衆のみなさんは音楽と真剣に向き合っていると感じ、そうした方々のために演奏するのはとても嬉しいことでした。
——2020年にはキャロライン・ショウの室内楽曲のアルバム「Orange」でグラミー賞を受賞しました。また今年9月にはショウ作品の2枚目のアルバム「Evergreen」もリリースされます。彼女の音楽との出会いは?
エイミー:最初に彼女の音楽を聴いたのはコロラドで聴いた彼女の声楽グループの演奏で、私もアンドリューも涙で顔がぐちゃぐちゃになりました。本当に美しく、しかもこのようなライヴ演奏をそれまで聴いたことがなかったのです。そしてこの時、私たちは彼女の曲をすべて演奏しようと決意したのでした——それまでハイドンとかベートーヴェンの全曲ツィクルスに取り組んできたのと同じように。私たちにとって現代作曲家の全曲演奏はそれが初めてでした。
アンドリュー:9月にリリースされたショウ作品の2枚目のアルバム「Evergreen」は2020年のパンデミックの最中にレコーディングされたものです。まだ検査もワクチンも出回っていない頃で、みんな不安の中でレコーディングしました——特にキャロラインはヴォーカルで参加していましたから。
私たちはコロナ禍に5枚のアルバムを制作しました。ちょうどドメニクが加わった直後にパンデミックになってしまったわけですが、その意味では現在の形でのアタッカ・クァルテットのサウンドはレコーディング・スタジオにおいて磨き上げてきたものと言ってもよいかもしれません。こうした時期を経て、ようやく4人で世界各地の舞台で演奏できることを待ち遠しく思っています。
アタッカ・クァルテット(弦楽四重奏)
Attacca Quartet

2003年に結成されたアタッカ・クァルテットは、2020年にグラミー賞(最優秀室内楽)を受賞し、アメリカで最も注目を集める弦楽四重奏団。古典派から現代音楽まで分野にとらわれず、歴史的奏法および解釈を重んじる演奏を取り入れ、常に新しい指針を求めて進化し続けている。第7回大阪国際室内楽コンクール優勝、第6回メルボルン国際室内楽コンクール第3位およびABCクラシックFM視聴者賞受賞など受賞歴多数。ジュリアード・クァルテットのアシスタント、メトロポリタン美術館のレジデント、テキサス州立大学のレジデントを歴任。これまでにジョン・アダムスの弦楽四重奏曲全集、ハイドン曲集などを録音。2021年にはソニー・クラシカルと専属契約を結び、弦楽四重奏の可能性を追求する新たな挑戦に取り組んでいる。アメリカ国内だけでなく、ヨーロッパ、南米、アジア、オーストラリアで精力的に演奏活動を展開しており、2014年にはアダムス作曲の弦楽四重奏協奏曲「アブソルート・ジェスト」のスペイン初演で好評を博した。
コロナ禍でもバンフセンター、オースティン室内楽センター、シュチェチン・フィル(ポーランド)などとデジタル配信の展開を進め、「アタッカ」(音楽用語で、楽章間を休みなく演奏し続けること)という名にふさわしく多忙な日々を送っている。