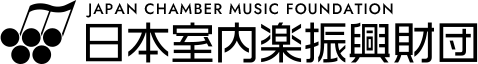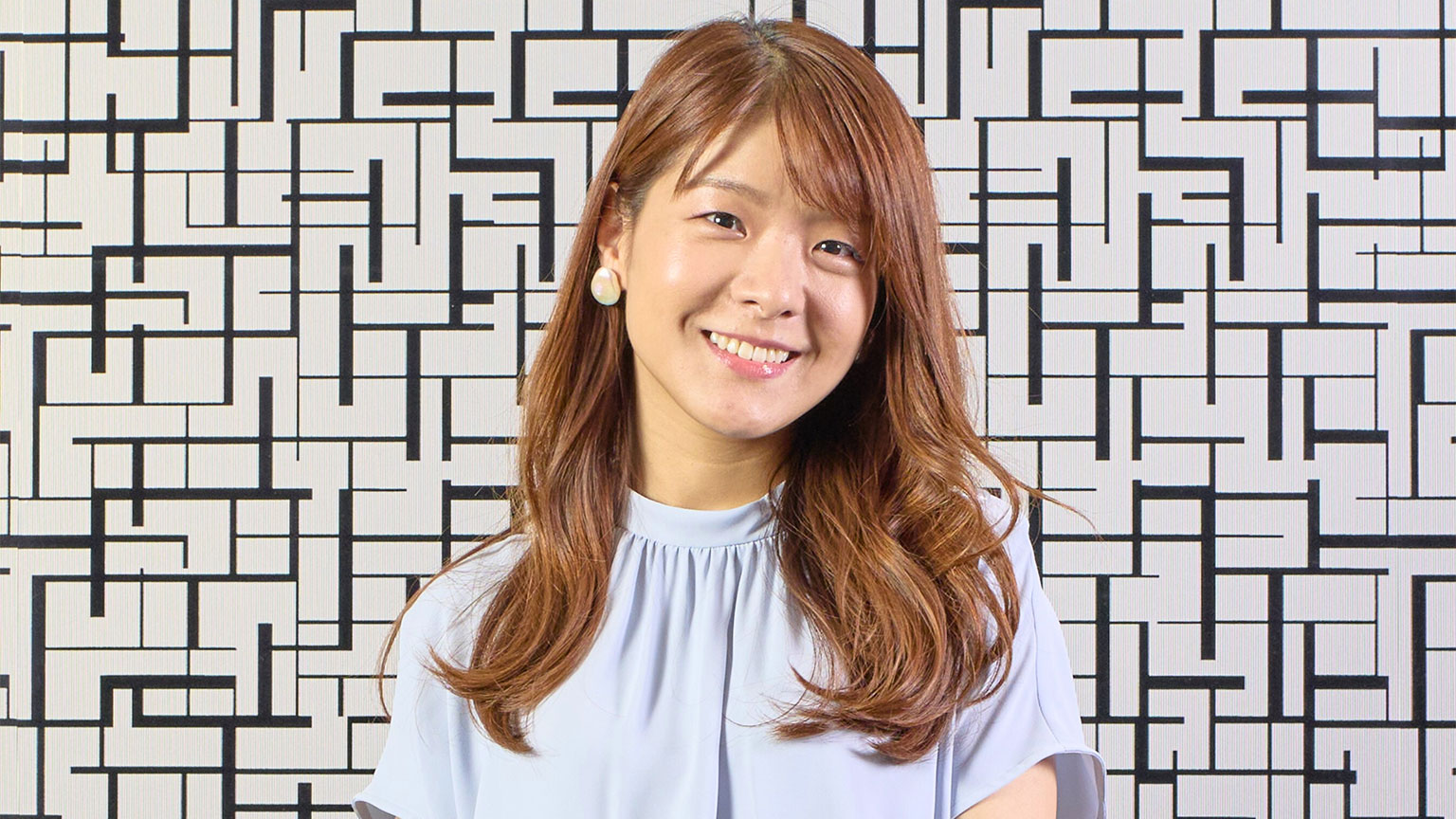
「奏」vol.64より
【対談】廣津留すみれさんに聞く 室内楽との出会いとその魅力
取材・文 高坂はる香(音楽ライター)

廣津留すみれ
(ヴァイオリン)
×
河井 拓
(大阪国際室内楽コンクール&フェスタ 総合プロデューサー)
生まれ故郷の大分でヴァイオリンを始め、18歳で渡米。
ハーバード大学、ジュリアード音楽院で学び、現在は演奏家としてだけでなく、起業家、著作家、コメンテーターとしても活躍する、廣津留すみれさん。
共通の音楽家の知人も多いという大阪国際室内楽コンクール&フェスタの河井拓総合プロデューサーが話を聞いた。
初めてのアンサンブル経験は、
ハーバード大学の室内楽クラス
河井 日本でヴァイオリンを習う子どもたちは、室内楽を経験する機会が少ないという現状がありますが、廣津留さんも子どもの頃はソロの勉強が中心でしたか?
廣津留 なにしろ大分ですから、そもそも〝この世で私以外にヴァイオリンを弾く人はいるのだろうか〞と思うくらい、周りにヴァイオリンをやっている子がいませんでした。同世代のレベルも全く知らず、CDで聴くハイフェッツやパールマンが唯一の比較対象でしたから、小学3年生で初めてコンクールに参加したときは、自分は彼らみたいに上手じゃないのに出ていいのだろうかと思っていました(笑)。ただそうして何も知らず、巨匠の演奏に憧れ、のびのび弾けていたのは逆に良かったのかもしれません。
別府アルゲリッチ音楽祭が身近だったことも大きかったです。ギトリスやマイスキーのような一流音楽家の仲間を連れてきて、毎年いろいろな室内楽作品を演奏してくれました。温泉や食を気に入ってくれたのか、キャンセルすることもなく! 当時はアルゲリッチが自分の街にくることが当たり前だと思っていましたが、とても恵まれた環境ですよね。
河井 そして高校3年生の1年で集中的に勉強して、ハーバード大学に合格されました。誰かと一緒に演奏することは、留学後初めて経験されたのですか?
廣津留 はい。ハーバードの学生は約6〜7割が楽器を演奏できると言われていて、上手な人もたくさんいます。室内楽の授業に登録したところ、彼らはユースオーケストラやジュリアード音楽院プレカレッジで顔見知りのようで、みんな事前にアンサンブルを組む約束をした状態でクラスをとっていました。大分上野丘高等学校から突然紛れ込んだ私はどうしようかと思いましたが(笑)、余ったメンバーの、ファゴット、フルート、ヴァイオリンという世にも珍しいトリオで、バッハの「音楽の捧げ物」をやることになりました。
ある日授業にゲストが来るというので誰かと思ったら、近所に住んでいたヨー・ヨー・マさんがふらっと現れました。私たち三人組もレッスンを受けることができて、この大学はとんでもないなと思いましたね。
またクラスではみんなの前で演奏したあと、お互いフィードバックをしなくてはいけません。授業で発言をするアメリカのスタイルには慣れてきていましたが、音楽のクラスでそれをするということは、同級生を批評するスタンスで聴くということ。簡単ではありませんが、お互い高め合えるおもしろい環境でした。
河井 そのあたりの感覚が求められるのは、ソロと室内楽の取り組みにおける大きな違いでしょうね。音楽を作るにあたって、自分たちがどうしたいか、意見を言い合うことが基本です。
廣津留 そうですね、特にアメリカの場合、異なる文化的背景の学生同士で演奏するケースが多いので、意見を伝え合わないとまとまりません。教育の現場ではリーダーシップについて考える機会が多く、そのうえで室内楽はとても良い題材だと思います。
私は秋田の国際教養大学で「Music Beyond Borders」という、音楽を通して教育や脳などの学問分野を学ぶ授業を担当しています。もちろん音大ではありませんが、リーダーシップについて考える回では、カルテットの演奏を見て誰がリードをとっているかを考えてもらいました。演奏しない人にとってはパッと見てもわからないものですが、実際、そこでどんなリーダーシップが働いているか、作品や場面でそれがどう変わるのかを考えると、多くのことを気づかせてくれます。

ジュリアードでカルテットを結成、
音楽へのアプローチに変化も
河井 卒業後はジュリアード音楽院に進まれました。ヨーロッパという選択肢もあったと思いますが、ニューヨークを選ばれたのはなぜですか?
廣津留 卒業後もアメリカに残りたいと思い、企業に入るかフリーランスで働くかと考えていたとき、ヨー・ヨー・マさんのシルクロード・アンサンブルと共演する機会がありました。メンバーにジュリアードの人もいらっしゃり、話を聞くうち、音楽ばかりに囲まれた環境で学ぶのも楽しそうだと思い、進学を決めました。
河井 室内楽に触れる機会が増えましたか?
廣津留 増えましたね! 2セメスターの室内楽クラスは必修だと新入生オリエンテーションで聞いて、たまたま近くに座っていた4人で弦楽四重奏を組みました(笑)。
カルテットはみんな同じタイプだとやりにくいことがありますが、相性もよく、役割分担もうまくできていました。アンソニア・カルテットと名前をつけて、MoMA(ニューヨーク近代美術館)やリンカーンセンターなどいろいろな場所で活動しました。
河井 固定メンバーで室内楽に取り組むことで、音楽へのアプローチは変わりました?
廣津留 ソロの時は弾きたいように弾けば良いですが、カルテットでは自分がどう弾くかが他の人のリアクションを変えるので、より責任重大です。例えば弓を最後にどう収めるかという細かいところも、グループで演奏するからこそ気を配るようになり、結果的にソロでも几帳面に気にするようになりました。予想外の影響です。
また私たちは誰かの意見に合わせるのではなく、それぞれの提案を試してから選ぶ民主的方法を大切にしていたので、コミュニケーションの末に弾き方を決めるという、ソロでは得られない経験ができました。コンセンサスが取れていない状態でレッスンに行くと、先生にすぐバレてしまいますからね。
河井 以前、東京クヮルテットの池田菊衛さんが、「カルテットを演奏することは、音楽家にとって大きな学びになります。同僚でもあり、時に批判をしてくれる先生でもある3人のメンバーとともに音楽を創ることは成長につながります」と話していました。他のメンバーから良いことばかり言われるわけではないと思いますが、それでも演奏家がカルテットをやりたいと思うのはなぜでしょう?
廣津留 まずすばらしいレパートリーがたくさんあるから、そして、そんな魅力的な曲をやっているとき、自分では気づかないアイデアをもらえるからでしょう。歳を重ねるほどそういう機会はより貴重になります。


タンゴで広がる音楽活動と、
クラシックとの違い
河井 最近は、「たぬきタンゴカルテット※」を結成されましたね。
廣津留 もともとジュリアードの修了リサイタルでピアソラが弾きたくて、アルゼンチン人のすばらしいバンドネオン奏者を呼んだことがきっかけで、ニューヨークでいろいろなタンゴ奏者と共演したり、ブエノスアイレスで録音したりする機会がありました。その後コロナをきっかけに日本に戻りましたが、やはりタンゴがやりたくてカルテットを結成したのです。
日本たぬきって、日本固有の生き物なんです。日本ならではのタンゴを海外に発信したいという思いでこの名前をつけました。あと、私が昔からたぬきが好きだというのも理由です(笑)。
河井 演奏している感覚は、クラシックの弦楽四重奏と違いますか?
廣津留 タンゴの人たちってキューを出さないんですよ。スッと息を吸って合わせることもせず、みんな前を向いて自分のことをやりながら、それが個々につながって一つの音楽ができるのが良い、という感じ。おもしろいですよね。即興も多いので、クラシックをやってきた身としてはやりがいがあります。タンゴはライフワークです。
河井 アメリカの室内楽協会ではジャズも室内楽のうちという定義があるくらいで、ジャンルについてボーダレスですね。
廣津留 日本ももっとそうなるといいですよね。技術的にもすばらしい方達がジャズやポップスに挑戦したら、すごいものができそう。そちらから入ってクラシックを聴く聴衆もいるでしょうし。
河井 私たち日本室内楽振興財団としては、そうして室内楽がもっと広まったらと思うのですけれど……統計的に、公演数はオペラやオーケストラとあまり変わらないのですが。
廣津留 呼び方を変えるのはどうですか!?クラシックに詳しくない方からすると〝室内楽〞といわれてもどういうものなのかピンとこないみたいですから。
河井 確かに、それは一つのアイデアかもしれません! 廣津留さんは教育の現場にも携わっていらっしゃいますし、室内楽を盛り上げるため、これからもよろしくお願いします。
※廣津留すみれ(ヴァイオリン)、清川宏樹(バンドネオン)、小林萌里(ピアノ)、小野としたか(コントラバス)の4人で結成されたタンゴ四重奏団。
PROFILE

廣津留すみれ Sumire Hirotsuru
ハーバード大学在学中より世界的チェリスト、ヨーヨー・マと度々の共演を経て、米国を拠点に演奏活動を展開。近年はソリストとしてデンマーク国立フィル日本ツアーや国内主要音楽祭に出演するほか、全国でリサイタルツアーを開催。ジャズトランペッターのクリス・ボッティとの海外公演やブエノスアイレスでのタンゴ録音など、ジャンルを超えて活動中。ジュリアード音楽院修了。国際教養大学特任准教授、第13期中央教育審議会委員。